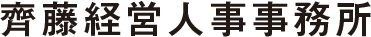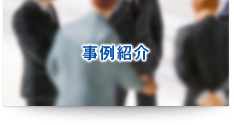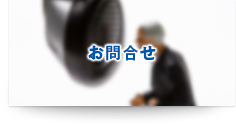お問い合わせはメールにて受け付けております
【労働判例に学ぶ人事・労務管理】年俸制の時間外手当(医療法人社団康心会事件、一審・控訴審・上告審)
 2018年05月28日
2018年05月28日
専門性が高い職種における年俸制の時間外手当について、年俸額に含まれるという賃金形態を採っているケースも少なくありません。このようなケースの考え方を示した裁判例として「医療法人社団康心会事件」を見ていきたいと思います。
医療法人社団康心会事件(一審 横浜地裁 平27.4.3判決、控訴審 東京高裁平27.10.7判決、上告審 最高裁二小 平29.7.7)
【事件の概要】
医療法人社団康心会(Y法人)が運営するN総合病院に勤務していた医師(X)が解雇され、Y法人による解雇は解雇権の濫用で無効であると主張し、併せて勤務中における時間外割増賃金の支払を求めた事件です。
Xは、平成24年4月にY法人と雇用契約を締結し、契約書の内容は次のとおりでした。
(1)年俸は1,700万円
① 本給(月額86万円)。
② 諸手当(月額34万1,000円、約付手当、職務手当、調整手当)。
※平成24年4月分のみ初月調整8,000円を加算。
③ 賞与(本給3か月分相当額を基準として成績により勘案)。
(2)勤務
① 週5日勤務。
② 1日の所定勤務時間は、午前8時30分から午後5時30分まで(休憩1時間)を基本とするが、業務の必要がある場合にはこれ以外の時間帯でも勤務しなければならない。その場合の時間外勤務に対する給与については「医師時間外勤務給与規定」に定める。
(3)医師時間外勤務給与規定
① 時間外勤務の対象となる業務は、原則として、病院収入に直接貢献する業務、または必要不可欠な緊急業務に限ること。
② 緊急業務における実働を対象として、管理責任者の認定によって支給すること。
③ 時間外手当の対象となる時間は、勤務日の午後9時から翌日の午前8時30分までの間、休日に発生する緊急業務に要した時間とすること。
④ 通常業務の延長とみなされる時間外業務は、対象とならないこと。
⑤ 当直・日直は、別に定める当直・日直手当を支給すること。
雇用契約においては「医師時間外勤務給与規定」以外の時間外労働等に対する割増賃金について、年俸1,700万円に含まれることが合意されていたが、年俸のうち時間外割増賃金に当たる部分は明らかにされていませんでした。
また、Xは労働基準法第41条2号の「監督もしくは管理の地位にある者」(いわゆる管理監督者)には該当していませんでした。
そして、Y法人はXに対し「医師時間外勤務給与規定」に基づき、合計27.5時間の時間外労働(うち7.5時間は深夜労働)に対する時間外手当として15万3,000円、当直手当として42万円を支払っていました。その際の時間単価の計算は、Xの1か月当たり平均所定労働時間と本給月額86万円を基礎として算出されたもので、深夜割増はされていましたが時間外労働の割増はされていませんでした。
【判決の主なポイント】
(1)解雇の有効性
(2)時間外割増賃金の有無
【判決の内容】
(1)解雇の有効性について
解雇の有効性については、一審・控訴審で判断されて上告審では棄却されたため、控訴審の判決で確定しました。判断は一審・控訴審とも同様のものでした。
Y法人の解雇理由としては、Xの勤務態度が悪いため普通解雇とされました。具体的には、
- 看護師に対する指示が曖昧にもかかわらず、指示に従った看護師を叱責。
- Xが提出した器具の購入申請書の記載に不備があったにもかかわらず、申請通り処理をしなかった担当者を厳しく責める。
- 看護師や研修医を指導する立場にありながら、指導において看護師の人格を否定するような発言や、有形力を行使(胸を叩いた)するなど指導方法も不適切。
- 看護学生や患者がいる場所で看護師を怒鳴ったり看護師と言い合うなど、看護学生や患者を不安にさせ病院の信用を低下させる恐れのある行為をした。
- 上記の行為により看護師がXに対する報告や指示内容の確認をためらうといった状況を生み、良質な医療の提供の前提となる看護師との連携を著しく困難にさせ、業務上の大きな支障を生じさせた。
このようなXの態度は、医療の提供というY法人の病院の中枢となる業務の遂行を困難にするものであり、本件解雇が客観的に合理性を欠き、社会通念上の相当性を欠くものということはできず解雇権の濫用には当たらない。つまり、解雇は有効とされました。
(2)時間外割増賃金の有無について
一審・控訴審では「医師時間外勤務給与規定」に基づき実際に支払われた時間外労働賃金と当直手当以外の通常の時間外労働賃金は、年俸に含まれるとされXの請求は棄却されました。しかし、最高裁では、時間外労働に対する割増賃金が年俸に含めて支払われたということはできないとして高裁へ差し戻されました。
(一審・二審の判断)
XとY法人との間の雇用契約において、時間外労働に対する賃金については「医師時間外勤務給与規定」に基づき支払われる時間外労働及び当直手当以外は年俸1,700万円に含まれているものとの合意したものと認められるとされました。
そして、その雇用契約の有効性について、Xの医師としての勤務及び責任に照らして合理性があるものと認められ、使用者の管理下における労務の提供という面においても自らの裁量で律することができたもので、月額120万1,000円という時間外労働に係る賃金が含められていると解しても不合理といえない好待遇な金額で、特に労働者としての保護にかける恐れがない、などという理由から有効性が認められました。
(最高裁の判断)
まず、割増賃金の意義として、労働基準法37条によって時間外労働に対する割増賃金を義務づけているのは、使用者に割増賃金を支払わせることによって時間外労働を抑制し、もって労働時間に関する規定を遵守させるとともに労働者への補償を行なおうとする趣旨であるとしました。
そして、基本給や諸手当にあらかじめ含める方法により割増賃金を支払う場合(いわゆる固定残業代制)、通常の労働時間の賃金に当たる部分と割増賃金に当たる部分とを判別することができることが必要であり(区分明確性)、その割増賃金に当たる部分が労働基準法37条により算定した割増賃金の額を下回るときは、使用者がその差額を労働者に支払う義務を負うべきとしました。
本件において、通常の時間外労働に対する割増賃金を年俸1,700万円に含めるという合意がされていたものの、年俸について通常の労働時間の賃金に当たる部分と割増賃金に当たる部分とを判別することができないため、年俸の支払いによってXの時間外労働及び深夜労働に対する割増賃金が支払われたということができないとされ、高裁へ差し戻されました。
つまり、固定残業代制は認められず時間外労働に対する割増賃金は年俸に含まれていないとされました。
【人事・労務管理のポイント】
●専門職で年俸制でも割増賃金の対象になる
医師のようなプロフェッショナルな職種で相当程度高額な給与を支給される者でも、労働基準法37条の割増賃金(残業代)の対象になります。医療機関においては、医師と医師以外の職員とで別個の就業規則を作成することが一般的ですが、医師の残業代はこの事件のように給与に含めるとしているものも少なくないようです。また、一般企業においても年俸制を採用している企業もありますが、この場合でも時間外労働に対する割増賃金の支払の対象になることに注意が必要です。
●固定残業代制の要件
次に、割増賃金を基本給や諸手当に含めて支給することについて、それ自体は直ちに労働基準法37条の割増賃金に違反するものではありませんが、割増賃金を基本給や諸手当に含めて支払う(固定残業代制)が認められるためには、二つの要件を満たす必要があります。
一つ目の要件は、給与の内訳として通常の労働時間の賃金に当たる部分と割増賃金に当たる部分都が判別できること、つまり給与額のいくらが残業代で残業時間が何時間分に相当するのかが明確に分かることが必要です(区分明確性)。実務上では就業規則へ給与に含まれる時間外労働時間数と計算方法を明記し、個別の給与額の明示の際に含まれる割増賃金額と時間外労働時間数を明示することが一般的です。
二つ目の要件は、給与に含まれる割増賃金の金額が労働基準法37条等に定められた方法で算定した割増賃金額を下回るときは、その差額を支払うことが必要になります。つまり、実際の時間外労働に対する残業代が固定残業代を超える場合は、その差額を支払っている、または支払う約束をしていることが求められます。
●定期的な就業規則の見直し
また、この事件ではY法人は「医師時間外勤務給与規定」に則って医師に対する時間外割増賃金を支給していました。つまり、就業規則通りに支給していたわけです。上記の二つの要件は、高知観光事件(最二小判平6.3.13)、テックジャパン事件(最一小判平24.3.8)、イーライフ事件(東京地判平25.2.28)、アクティリンク事件(東京地判平24.8.28)などの最近の事件から確立してきた判断基準です。そうすると、企業において以前から就業規則通りの運用をしていると、いつの間にか判断基準が変わっているケースも少なくないため就業規則は定期的に見直しておく必要があります。